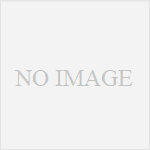「やのあさって」はどこの言葉?

「やのあさって」は岩手県の方言だよ。
「やのあさって」は標準語で?
やのあさって
標準語で、『しあさって(明々後日)』

「やのあさって」は、標準語の『しあさって(明々後日)』と同じ意味だよ。
「やのあさって」はどういう意味?
「やのあさって」は明々後日のことを言います。
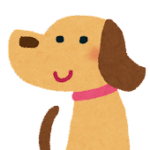
標準語では、明々後日の次の日、つまり4日後のことを指す言葉なんだ。
場所によって違うと混乱しちゃうよーーー!!
「やのあさって」は東日本地域全般で使われています。
「やのあさって」の語源・由来

一般的には、「あしたーあさってーしあさってーやのあさって」と言うことが多いです。
国語辞典にもこのように記載するものが多いです。
ところが、東京を除く関東などでは、「しあさって」と「やのあさって」の指す日が逆転し、「あしたーあさってーやのあさってーしあさって」のように数える地域が広がっています。
「しあさって」の「し」は「再来週」の「さ」と同類で、「さらに」という意味を添える接頭辞です。
また、「やのあさって」の「や」は「いやいやますます」「いやが上にも」などの「いや」と同源で、やはり「さらに」という意味です。
つまり「しあさって」と「やのあさって」はどちらももともとは、「明後日の翌日」の意味でした。

全国的にみると、「あさっての翌日」の言い方として、東に「やのあさって」、西に「しあさって」が広く分布しています。
しかし西の言葉の勢力は強く、江戸時代には関東に進出しようとしました。
その際、西日本(特に上方)から直接の影響を受ける江戸と、その周辺で江戸を通して間接的に影響を受ける関東とでは、採り入れ方に違いが生じました。
江戸では、上方の「しあさって」を語形・意味ともそのまま取り入れ、従来の「やのあさって」は、意味が「あさっての翌々日」にずれて残りました。
周辺の関東方言では、従来の「やのあさって」はそのまま残り、上方の「しあさって」が「あさっての翌々日」の意味にずれて取り入れられました。

地域によって指し示す日にちが違うので、注意が必要ですね。
「やのあさって」の使い方

じゃあ、やのあさってに会おう

えーと、今日が十一日だから、十五日だね。

違うよ、十四日だよ。

えっ?
十四日はしあさってじゃん?
「やのあさって」の例文

こんどのあずまりは、やのあさっでだがら、わすれるなよ

今度の会合はしあさってだから忘れないようにね